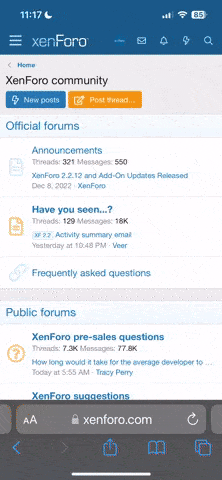深夜の路地を少女は必死になって「何か」から逃れようと走っていた。
誰もいないはずの背後から禍々しい気配とともに聞こえてくる足音。
振り返っても誰もいない。
しかし、歩き出すと同じ歩調で聞こえてくる足音。
少女は学校で聞いたばかりの都市伝説を思い出していた。
「誰もいない夜道なのに後ろから足音きこえてくるんやって」
「どれだけ早く走っても、どれだけ遠くまで逃げてもぴったりとあとについてくるんだ」
「そいでな、袋小路とか行き止まりにいってしまうと『捕まってひどいこと』されてしまうんやって」
学校で友達から聞いた時、少女はそんな馬鹿らしい話あってたまるものですか、と一笑に付しそのあとすぐに受けた授業などで忘れていた。そして忘れていたがためにいつもどおり深夜にコンビニへ行ってしまったのだ。コンビニからの帰り道、あの足音を聞いて思い出した。
しかし時すでに遅く、少女は両親の忠告を無視してコンビニに行ったことへの後悔と足音から逃げる以外術はなかった。
深夜の路地を駆ける。肩で荒く息をしながら、決して後ろを振り返るようなことはしない。後ろを振り返っても「誰もいない」ことが分かっているからだ。
無駄なことをして体力や気力を使うより、一瞬でも早く自宅に帰りつくために前だけを見て走った。
しかし少女の努力をあざ笑うかのように、少女の歩調とほぼ同じ速さで聞こえてくる足音。わずかにだけ早く、気配は徐々にだが少女との距離を詰めている。
「たしか、こっちのほうが近道のはずっ」
そう思い少女は右へ左へ路地を進んでいく。なるべく人通りのありそうな道を織り交ぜながら進んでいるはずなのだがなぜか人通りの少ない、だんだん道幅が細くなるところへといってしまう。少女がよく知ったはずの道は期待通りの場所に行きつくことさえできず全然違う、よく似た『別の世界』に放り込まれたかのような気にさせる。
駆ける度、揺れる少女の胸。すでに息は荒く本来ならもう走ることはおろか歩くことさえできないほど少女は疲労していたが、後ろから聞こえてくる「ぺたぺた」という足音が恐怖を生み、その恐怖が皮肉なことに少女に走る気力を与えていた。
しかし物事には始まりと終わりがあり、物語には結末がある。
ついに少女にも結末が来てしまったのだ。
最後に十字路を右に折れ、長く続くであろうと思われた路地を走っていたところ、ぽつんとあった街路灯に差し掛かった時、先に見えたのは無情にも袋小路となったブロック塀だった。少女にはそれが嘆きの壁にみえ、また少女の行く先を暗示していたかのようだった。
壁をみてへたりこんだ少女の背後に、無情にも『ソレ』はやってきた。
ぺたん、ぺったん。
わざわざ聞こえるようにゆっくりと、足音高く。
ぺったん、ぺたん。
一歩一歩確実に、少女に近づいてくる。
気がついた時には少女の真後ろから気配がする。少女の耳朶には『ソレ』の息遣いが聞こえる。
少女の脳裏には絶望と、学校で聞いた「末路」が走馬灯のように映し出される。
「そいでな、アレに捕まるとxxxx奪われてしまうんやって」
あどけなく笑いながらいう彼女の表情が脳裏で再生された直後、少女は強い力で肩を掴まれ……
クラスの男子の視線を集めるぐらい育っていた胸が跡形もなくなくなっており、文字通りつるつるのぺたぺた、になっていたのだ。
21世紀、科学が支配する日本にあってまだ語り継がれる都市伝説に曰く『ぺたぺたさん』の怪異である。
あな、おそろしや。